プリント基板の設計は、
CAD上で問題なく設計できていても、
それが正しい設計とは限りません。
実際には、基板製造や実装の工程を考慮した設計ができていないと、
試作段階で不具合が発生したり、
量産時に手直しが必要になったりするケースが発生します。
プリント基板設計に長く携わってきたベテラン設計者であれば、
その経験や知識から自然に対処できる設計上のポイントも、
若手設計者の方が基板設計に取り組む際には
見落とされてしまう重要なポイントがいくつかあります。
そこで今回は、特に若手設計者の方に向けた
「基本だけど、見落とされやすい基板設計の3つのポイント」
について具体的に解説いたします。
見落とされやすい基板設計の3つのポイント
ポイント①:部品の極性が明示されていないことで発生する逆実装を防ぐ
コンデンサ、ダイオード、LEDなど極性部品は、
基板上で向きが明確になるようにする必要があります。
極性部品の向きが不明確の場合、
実装工程で部品が逆に搭載されてしまうことがあります。
対策としては、基板のシルクに
ダイオードの場合は、カソード側には線を入れる、
電解コンデンサはプラス側に「+」を明記するなど
が挙げられます。
また、高密度実装など、部品を詰めて配置した場合、
シルク(部品の外形や極性マーク)が
隣のパッドに重なってしまうことがあります。
特に下記のように1ピンを示すシルクがパッドに重なっていた場合、
基板製造時に消えてしまう可能性があります。
1ピンや、極性の向きを示すシルクが消えてしまうと、
部品実装時に向きの判別が出来ず、逆実装に繋がってしまいます。
図1.シルクとパッドの重なり
そのため、極性のある部品は1番ピンや極性を示すシルクが重ならないように、
下記のようにスペースを確保した上で配置を行う必要があります。
図2.シルクとパッドの重なりの対策例
極性部品の向きを分かりやすくすることで、
実装不良やリワーク発生を防止し、
無駄なコストや手間をかけずに部品実装を行うことができます。
ポイント②:部品と基板端との距離を十分に取り、無駄な工数の発生を防ぐ
部品と基板端との距離が短すぎると、
マウンタでの実装ができず、後付けでの対応となり、
工程が増えてしまいます。
また、マウンタでの実装ができない場合、
手作業での実装となるため、
工数がかかる可能性があります。
そのため、一般的には、部品と基板端との距離は5mm以上空けるようにします。
基板端と部品の距離が1㎜などどうしても近づける必要がある場合には、
「捨て基板」を追加して対応します。
捨て基板を追加することで、
基板面積が増えるためコストがかかるという点がありますが、
品質を安定させることが可能です。
ポイント③:基板内の認識マークを非対称に配置し、基板の誤認識を防ぐ
実は意外と見落とされがちなのが、
基板内の認識マークです。
基板に部品を自動で実装する際、
マウンターはカメラで基板の位置を認識します。
この基準となるのが認識マークです。
この認識マークは、特に捨て基板が無い場合や、
小型・高密度の基板で、部品配置スペースが限られている場合などで
製品内に入っていないことがあるので、注意が必要です。
また、認識マークを配置する際には、下記のように
左右非対称になるように配置することに注意が必要です。
図3. 基板内の認識マーク
仮に認識マークが左右対称で、
マウンタへの投入方向を180°間違えてしまった場合、
基板が誤って認識されてしまいます。
認識マークの位置が上記のように左右非対称であれば、
基板を投入した時点で マウンタの認識が取れず、
間違いに気づくことができます。
まずは認識マークに見落としがないかを確認し、
その上で左右非対称になっているかを確認して、
設計を行う必要があります。
プリント基板はアート電子までお任せください!
今回は、見落とされがちな設計項目として、
特に押さえて頂きたい3つのポイントを解説いたしました。
ここで押さえて頂きたいのは、
その後の製造工程を考慮した上で設計を行うことで、
品質向上やリードタイム削減を実現できるということです。
当社では、プリント基板に精通したエンジニアが
設計に問題ないかどうかをモノづくりの視点からサポートしています。
各種基板の回路設計やパターン設計、試作実装から量産まで
構想・仕様さえお聞かせ頂ければ
設計・調達業務をすべてお任せ頂くことも可能です。
プリント基板の開発に関するお悩みは、
お気軽にアート電子にご相談ください。
また、当社ではその他の多数の技術情報をWEBサイトにアップしていますので、
ご興味をお持ちの方はぜひご一読頂ければと思います。







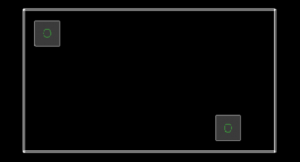
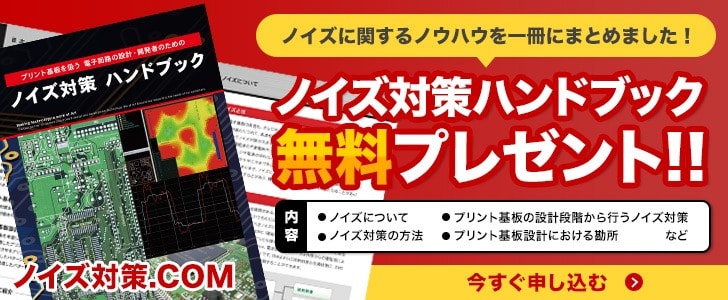

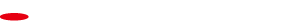 プリント基板のアート電子株式会社
〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館
プリント基板のアート電子株式会社
〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館